PMS(月経前症候群)と腸内フローラの関係|最新研究をもとにした対策のヒント【近畿大学武田先生監修】

INDEX
PMS(月経前症候群)による不調、実は”腸”に関連があった?近畿大学が解明した、PMSと腸内フローラの関係とは
生理前になるとイライラする、気分が落ち込む、頭痛や関節痛が起きやすい、むくみやすくなる──。そんな症状に悩む女性は少なくありません。これは「PMS(月経前症候群)」と呼ばれるもので、女性の約8割が何らかの不調を感じているとも言われています。
これまで、PMSの原因はホルモンバランスの変化とされてきましたが、近年「腸内環境との関係」に注目が集まっています。そんな中、近畿大学東洋医学研究所を中心とする研究チームが、PMSと腸内フローラが強く関係していることを世界で初めて解明しました。この記事では、最新研究の内容をもとに、そこから見えてきた新たなPMS対策の可能性をご紹介します。
・最新研究により、PMS(月経前症候群)の症状と腸内フローラが関係していることが明らかになった。 ・PMS患者では、特に精神安定に関与する「酪酸菌」「GABA産生菌」が減少している ・腸活によって、PMS症状の改善が期待される可能性がある。
日本人女性の半数以上が悩むPMS(月経前症候群)とは

PMS(月経前症候群)とは、月経前に現れるこころとからだの不調のことを言います。イライラや落ち込み、不安感といったこころの不調や、腹部膨満感、乳房の張りなどのからだの不調が、月経前の3〜10日間くらい続き、月経が始まると自然に和らぐのが特徴です。
日本人女性の半数以上がPMSに悩まされていると言われており、日常生活や仕事へ大きく影響を与えることもあり、女性の健康に関する社会問題としても注目されています。
PMS(月経前症候群)の原因と治療法

はっきりとした原因は明らかになっていませんが、月経周期に伴う女性ホルモンの変動が影響していると考えられています。その他にも、ストレスなど様々な要因が重なりあって不調に繋がると考えられています。
一般的な治療法としては、低用量ピルの服用で排卵を抑える、症状や体質に合わせた漢方薬を用いる、脳内のセロトニンを増やす薬の服用、痛みやむくみ等の不調に対する対症療法、などがあります。
【世界初】PMS(月経前症候群)と腸内フローラの関係性に関する研究
近畿大学東洋医学研究所により2022年に発表された研究*で、PMS患者と健常者の腸内フローラを比較した世界初の調査が行われました。その結果、PMS患者には以下の特徴が見られました。
PMS患者の腸内フローラの特徴
・抗うつ作用が期待される酪酸菌(Butyricicoccusなど)や、脳内神経伝達物質GABAを産生する菌(Megasphaeraなど)が減少している ・PMS症状の重症度と、特定の腸内細菌(Parabacteroides、Megasphaeraなど)の割合に相関がある ・これらの腸内細菌の特徴は、うつ病患者で報告されているものとは異なる
具体的には、PMS患者ではButyricicoccus、Extibacter、Megasphaera、Parabacteroidesが少なく、Anaerotaeniaが多いという分布が明らかになりました。特に、ParabacteroidesやMegasphaeraの割合が多いほど、PMS症状が軽くなる傾向が認められました。

* Takeda T, Yoshimi K, Kai S, Ozawa G, Yamada K, Hiramatsu K (2022) Characteristics of the gut microbiota in women with premenstrual symptoms: A cross-sectional study. PLoS ONE 17(5): e0268466. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268466
腸内フローラがPMS(月経前症候群)に与える影響
腸内フローラは、脳と腸の相互作用(脳腸相関)を通じて、心の健康にも大きな影響を与えることが知られています。特に、酪酸菌は、抗炎症作用や腸内環境の改善、さらには精神安定作用が期待されており、GABA産生菌は不安やストレスの緩和に関与すると考えられています。
PMS患者でこれらの細菌が減少していることは、腸内フローラの乱れがPMS症状の発現や症状の重さに繋がっている可能性を示しています。
【関連記事】 脳腸相関とは?脳と腸が相互作用するメカニズムとセロトニンの関係を解説【管理栄養士監修】
腸から始まる、新しいPMS(月経前症候群)対策とは?

今後は、これまでの治療法に加えて、腸内環境を整えることによるPMS対策の可能性が期待されています。腸内環境を整えるためには、プロバイオティクス(発酵食品など)やプレバイオティクス(水溶性食物繊維など)を含むバランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠といった生活習慣全体を改善することが大切です。
特にプレバイオティクス(水溶性食物繊維など)は、最新研究でもPMS症状と関連が深いとされていた酪酸菌のエサとなりやすいため、大麦や海藻類、きのこ類などを積極的にとりいれると良いでしょう。
PMSのつらさに悩む女性にとって、腸活がホルモンや薬に頼らずに体調を整えられる、新しい選択肢になるかもしれません。
【関連記事】
・腸内フローラ(腸内細菌叢)を整える食べ物の特徴【管理栄養士監修】
・腸内フローラ(腸内細菌叢)を改善する方法について【管理栄養士監修】
まとめ
日本人女性の多くが悩まされているPMSですが、最新の研究成果から、腸内フローラにも関係性があることが明らかになりました。特に酪酸やGABAを産生する細菌が減少しており、これが症状の一因となっている可能性が示唆されています。
今後は、腸内フローラを整えること(腸活)で、ホルモンや薬に頼らない新たなPMSケアが実現するかもしれません。
監修
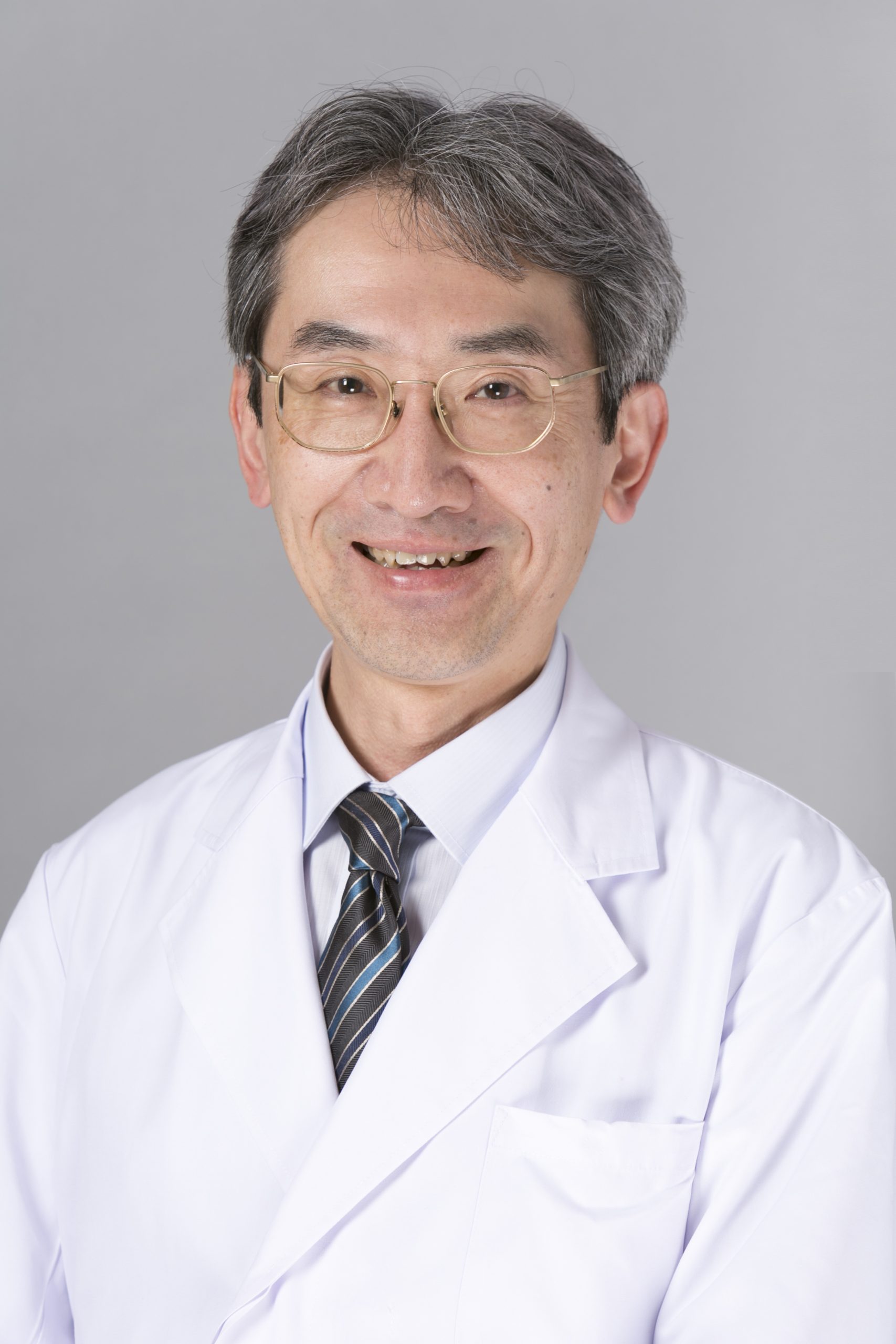
近畿大学東洋医学研究所 所長・教授 武田 卓 先生
監修コメント
今回の研究では、PMSの症状と腸内フローラとの関係が明らかになり、私自身も驚くような新しい発見がありました。これまでホルモン変動が主な原因とされてきたPMSですが、腸内環境という新たな視点からのアプローチで、今後の診断やケアの方法が大きく変わっていく可能性があります。
PMSは多くの女性が日常的に悩んでいるにもかかわらず、その実態はまだ十分に解明されていません。症状の重さや影響の大きさは千差万別ですが、「つらいのに相談しづらい」「薬に頼ることに抵抗がある」と感じている方も少なくないのではないでしょうか。だからこそ、一人ひとりの体験やデータが、次の研究の大きな力になります。
今後も更に研究を重ね、PMSと腸内環境の関係性を解明していきたいと思います。
プロフィール
1987年大阪大学医学部卒業、1995年同大学大学院博士課程修了
1997年 大阪大学医学部 助手(産婦人科教室)
1998年 大阪府立母子保健総合医療センター 産科診療主任・医長
2001年 大阪大学医学部 助手(産婦人科教室) 2004年 大阪府立成人病センター 婦人科 副部長
2007年 大阪大学医学部 助教(学内講師)(産婦人科教室)
2008年 東北大学医学部 准教授(先進漢方治療医学講座)
2012年より近畿大学東洋医学研究所所長・同女性医学部門教授。東北大学医学部産婦人科客員教授。漢方・産婦人科・腫瘍・内分泌の専門医として、女性のヘルスケア全般を西洋・東洋医学の両面から研究。特に女性心身症(更年期・PMS)、がん患者愁訴、冷え症、フェムテックなど。
近畿大学東洋医学研究所



